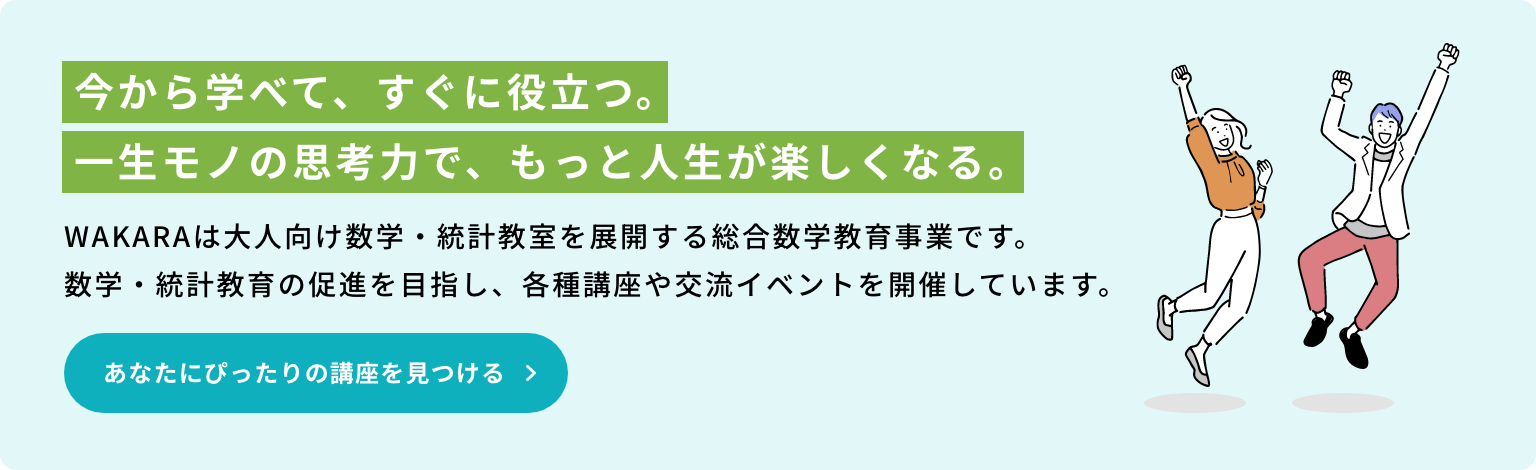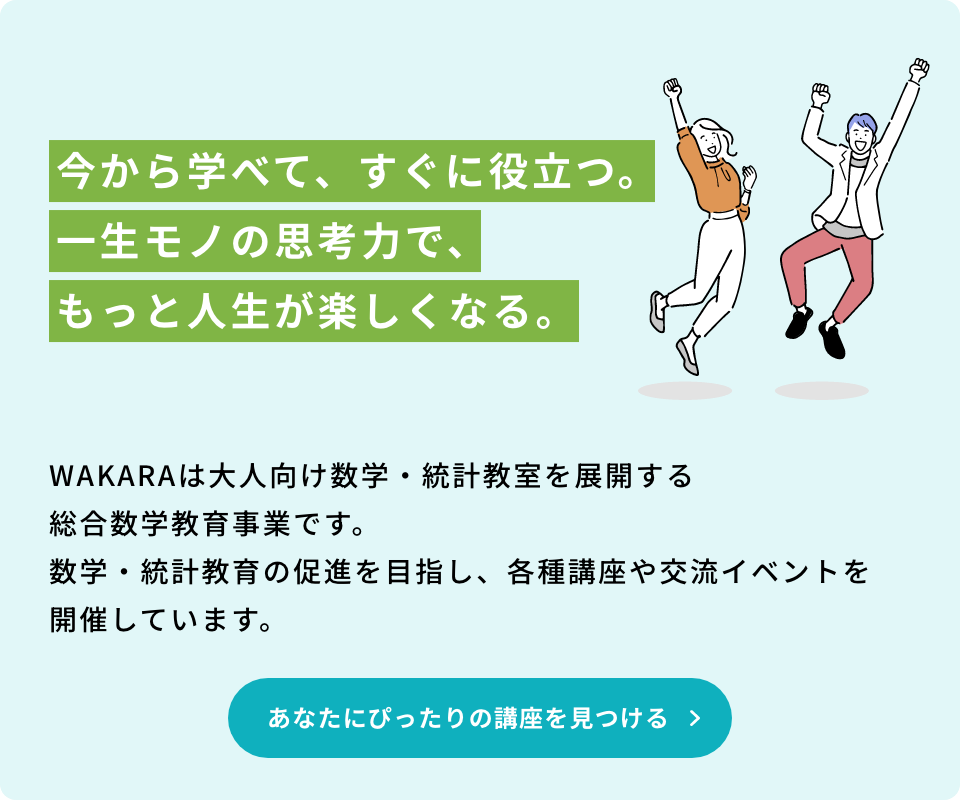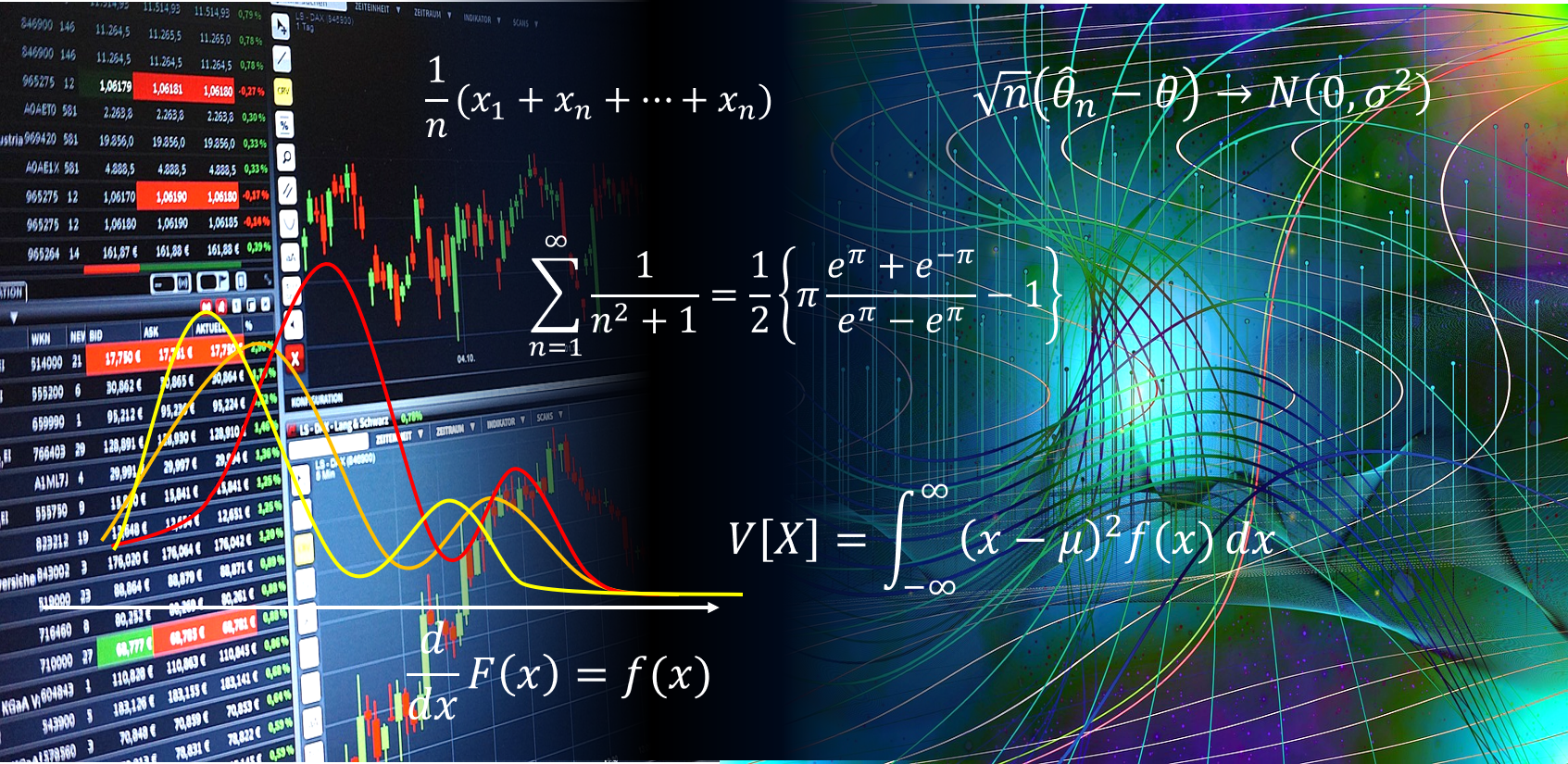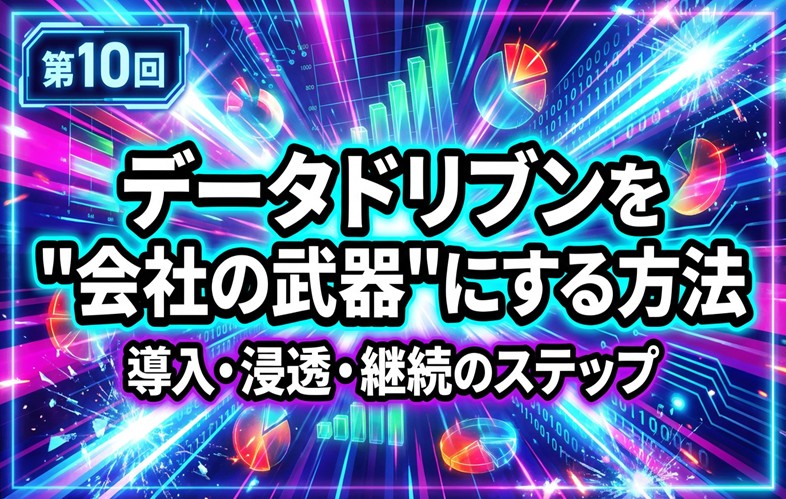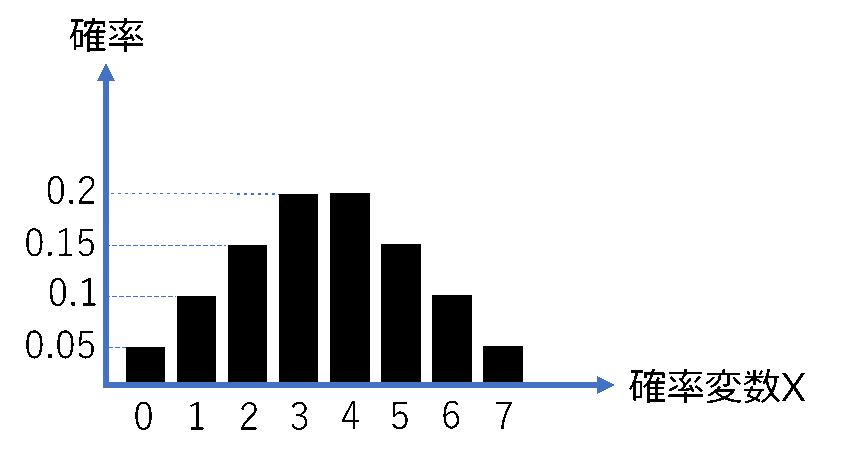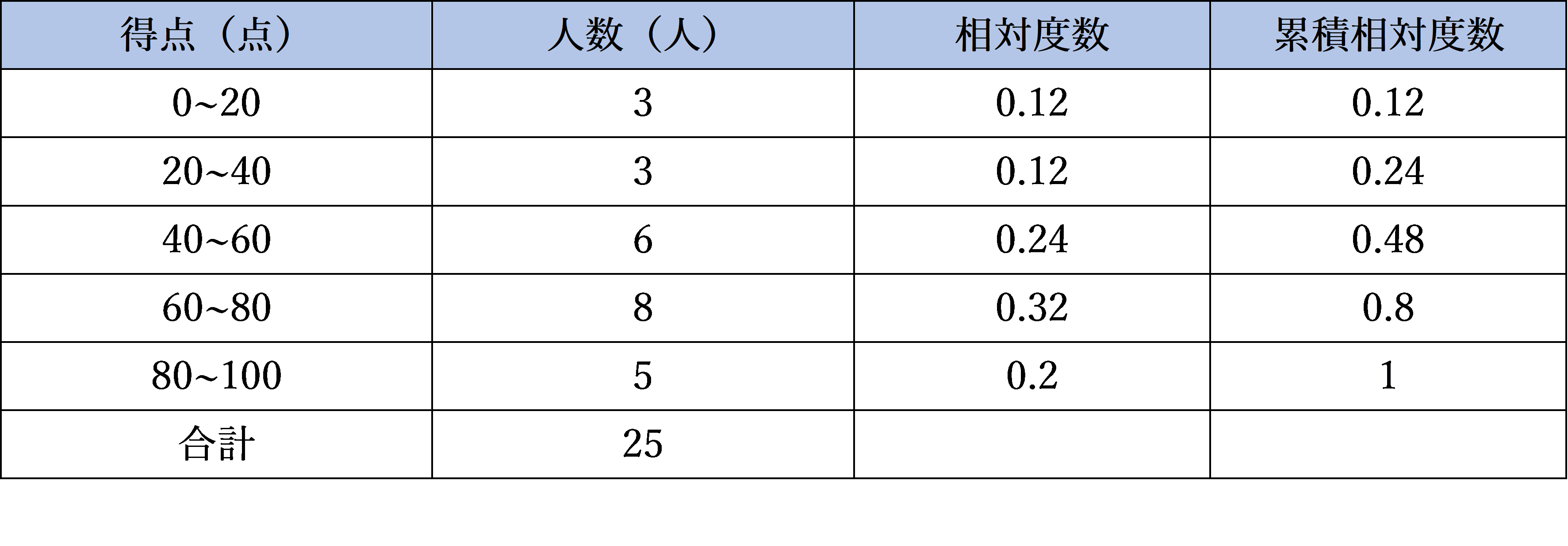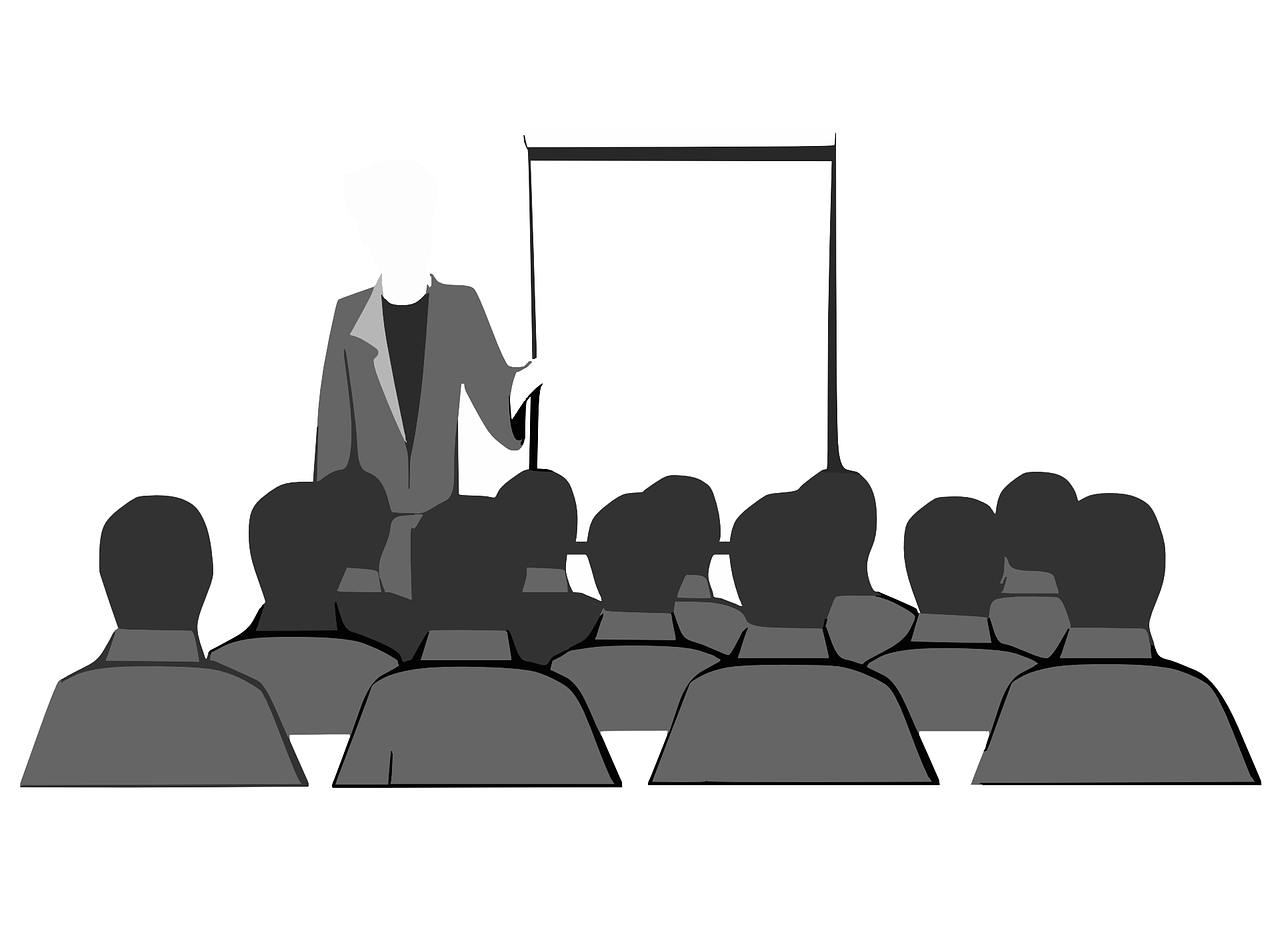【和から株式会社】AI(人工知能)超入門
公開日
2024年11月19日
更新日
2025年2月9日
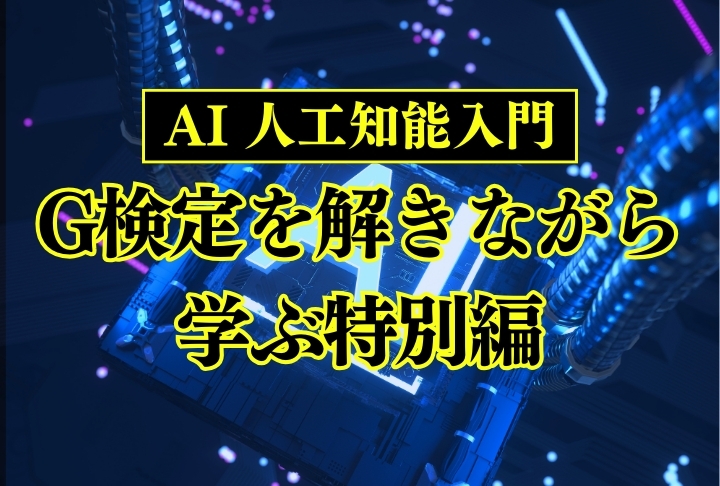
和から株式会社主催「AI(人工知能)超入門」講義のご紹介
和から株式会社が主催する「AI(人工知能)超入門」の講義の様子をご紹介します。
AIについて知りたい方、これから勉強を始めたい方は、ぜひご参加ください。
▼講義の様子は動画でもご覧いただけます▼
AIに対する正しい理解を深めよう
近年、AI(人工知能)は私たちの生活に深く浸透し、多くの企業や研究機関が注目しています。
例えば、日本企業の特許出願数を見ても、東芝、NEC、富士通、日立、ソニー、トヨタなどの大手企業が世界的にも多数のAI関連特許を保有しており、その影響力は計り知れません。
しかし、「AIとは何か?」という問いに明確に答えられる人は意外と少ないのが現状です。
ニュースやメディアの影響で、AIは「何でもできる万能な技術」と誤解されがちですが、実際にはできることとできないことがはっきりと分かれています。
本講義では、AIの基本概念を理解し、どのように活用できるのかを学びます。
AIに対する漠然とした不安や誤解を解消し、「どう使いこなすか?」という視点を持っていただくことが目的です。
AIの基礎:できること・できないこと
まず、AIがどのような分野で活用されているのかを知ることが重要です。
また、AIを正しく活用するために必要な知識やスキルについても触れていきます。
講義の中では、次のような疑問にもお答えしていきます。
AIとはそもそも何か?
ディープラーニングやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)との違いは?
AIを使うことで、新しい仕事は生まれるのか?
AIに使われないために、何を学ぶべきか?
最近では、「AI」「ディープラーニング」「RPA」などの言葉が混同されがちです。
実際、ディープラーニングはAIの一分野であり、RPAは業務の自動化を目的とした技術でありながら、AIとは異なる概念です。
これらの違いを明確に理解することで、AIを適切に活用できるようになります。
AIの歴史:過去から学ぶ
AIを正しく理解するには、その歴史を知ることが重要です。
技術がどのように発展し、どのような課題を経て現在に至ったのかを学ぶことで、AIの本質を見極める手助けになります。
AIの歴史は、大きく3つのブームに分かれます。
第1次AIブーム(1950年代~1970年代)
AI研究の始まり
1956年、「人工知能(Artificial Intelligence)」という言葉が誕生(ジョン・マッカーシーによる命名)
当時の研究は、コンピューターを使った推論や探索に焦点を当てていた
エキスパートシステムやファジーシステムの登場
第2次AIブーム(1980年代~1990年代)
ルールベースのAIが発展
しかし、処理能力の限界とデータ不足により、期待通りの成果を出せなかった
第3次AIブーム(2000年代以降~現在)
ディープラーニングの台頭により、画像認識や自然言語処理が飛躍的に向上
ビッグデータの活用により、AIの実用化が進む
自動運転、医療診断、マーケティング分析など、多くの分野で実用化
AIは「万能」ではない—正しい知識が重要
現在、多くの企業がAIを導入しようとしていますが、「目的のないAI導入」は、単なる流行の波に乗るだけで終わってしまう可能性があります。
例えば、「AIを導入すれば業務がすべて自動化される」と考える企業もありますが、実際には適切な設計やデータの準備が必要です。
また、「AIを使えばすべての問題が解決する」と誤解されることも多いですが、AIはあくまで一つのツールに過ぎません。
この講義では、AIを活用するために必要な知識を身につけ、実際のビジネスや日常生活にどのように応用できるのかを考えていきます。
まとめ
AIは「万能」ではない
できることとできないことを正しく理解することが重要
AIの活用には目的が必要
ただ導入するのではなく、具体的な課題解決に向けて活用すべき
正しい知識が必要
AIに対する誤解をなくし、適切に活用するための知識を身につける
本講義では、AIの基本から実践的な活用方法までを学びます。
AIに関心のある方、これから学び始めたい方は、ぜひご参加ください!