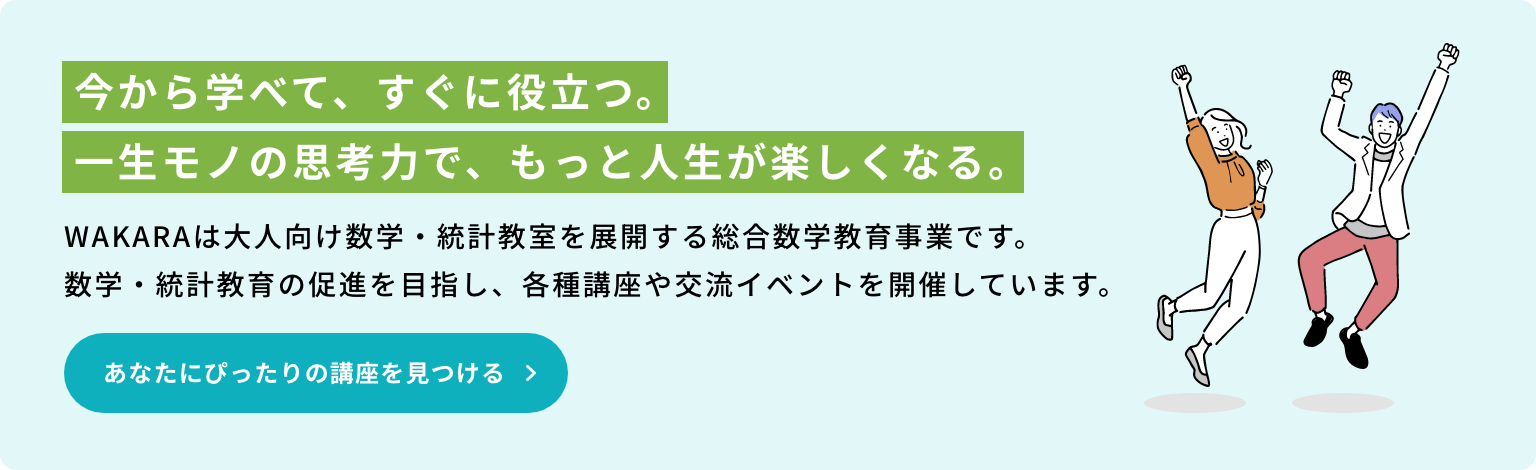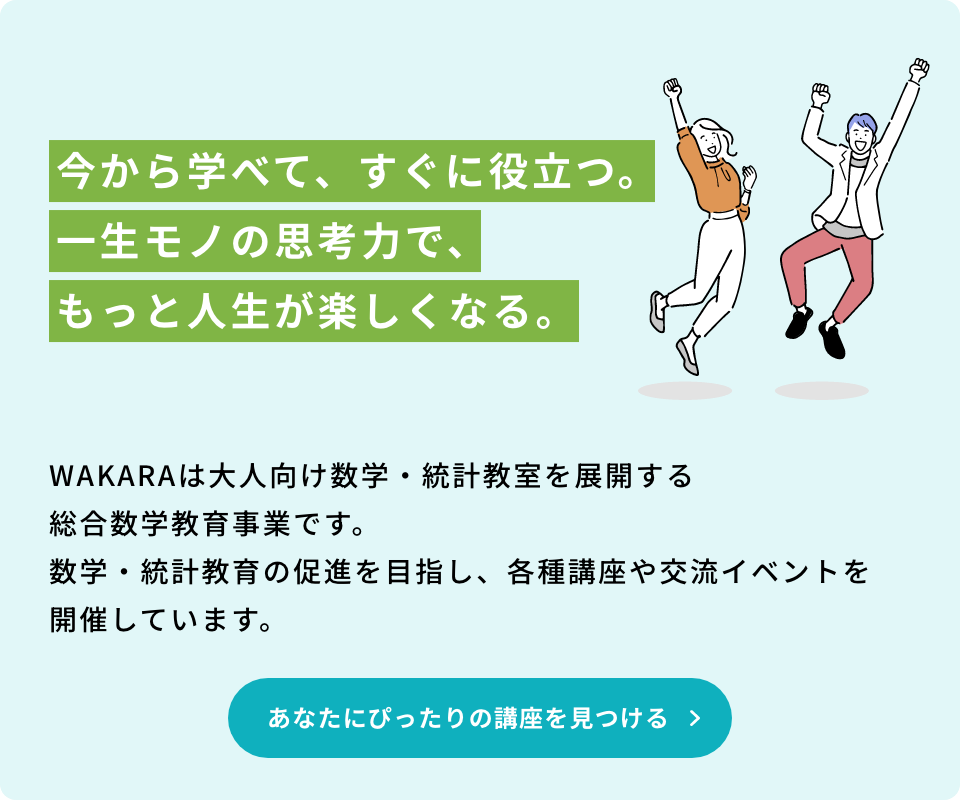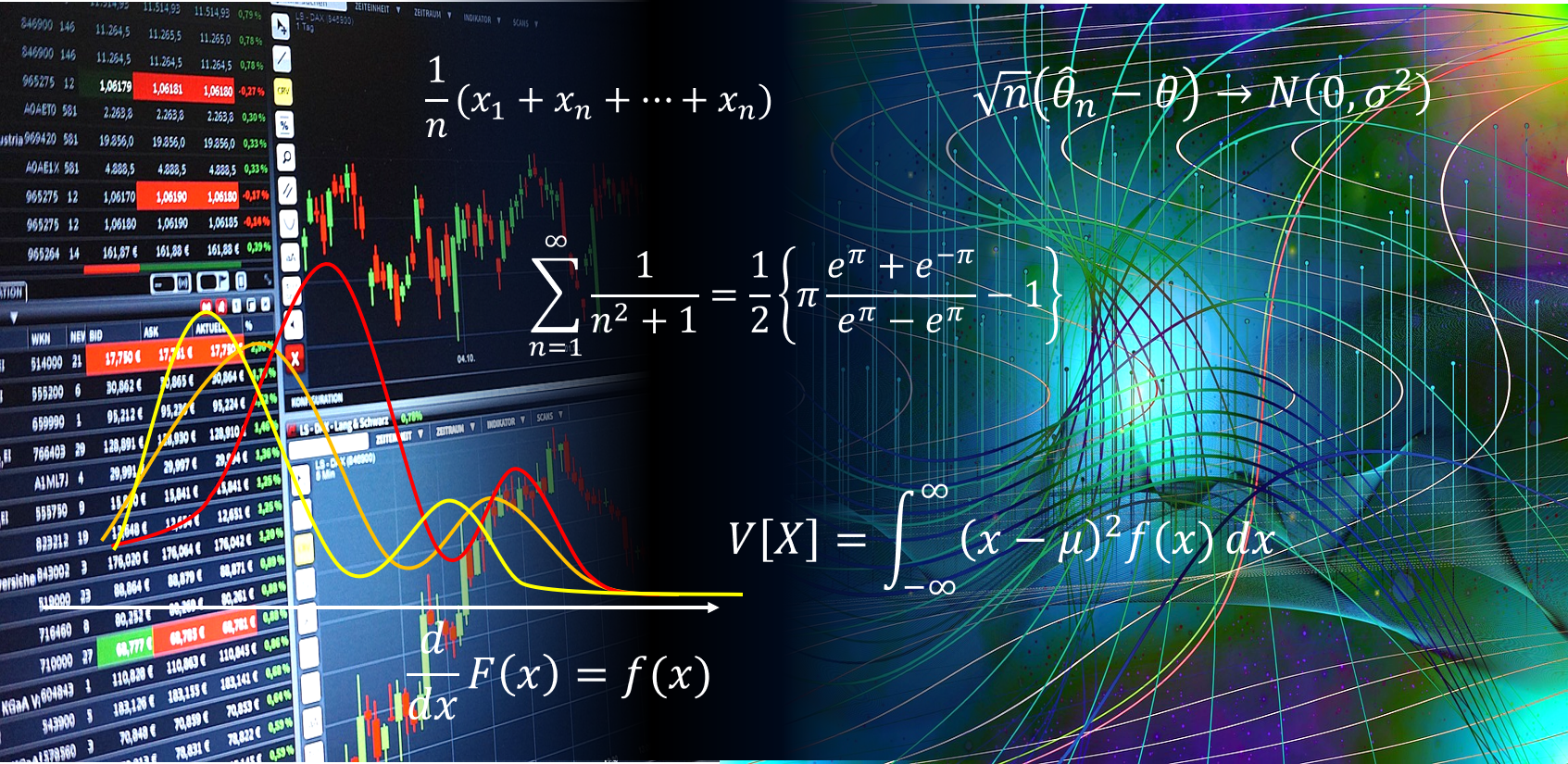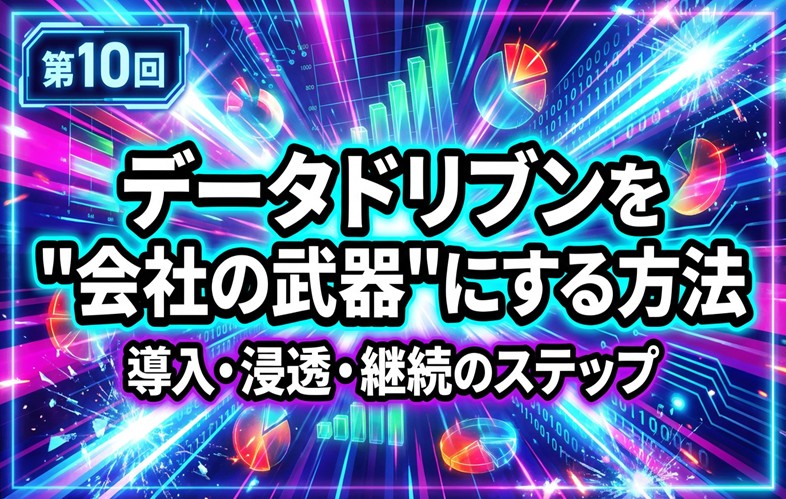【算数からやさしく解説】空間図形(立体)の総復習(三角柱・三角錐編)
公開日
2025年2月18日
更新日
2025年9月17日

【算数からやさしく解説】空間図形(立体)の総復習(三角柱・三角錐編)
皆さんこんにちは!今回も空間図形についてお話ししていきます。
前回は直方体や立方体について解説しましたが、今回は三角柱と三角錐に注目して、それぞれの特徴や違いを詳しく見ていきましょう。
空間図形とは?(復習)
まず、空間図形とは何かをおさらいしておきます。
空間図形(立体)とは、平面図形に高さが加わったもののことです。例えば、円に高さを加えると円柱になり、三角形に高さを加えると三角柱になります。
また、立方体や直方体も空間図形の代表例です。このように、平面図形を積み重ねたり、先端をとがらせたりすることで、さまざまな立体が作られることを理解しておきましょう。
三角柱とは?
三角柱とは、上下の面が同じ三角形で、それをつなぐ側面が長方形になっている立体のことです。
この立体をイメージするには、平面上に三角形を描き、それを高さ方向にまっすぐ伸ばすと考えると分かりやすいでしょう。
三角柱の特徴として、頂点が6個、辺が9本、面が5枚あります。
例えば、テントや屋根の形をした建物などが三角柱の形をしています。
三角錐とは?
三角錐とは、底面が三角形で、頂点が1つに集まる形の立体です。ちょうど三角形のピラミッドのような形をしています。
三角柱とは異なり、上の面がすぼまっているのが特徴です。
三角錐の特徴として、頂点が4個、辺が6本、面が4枚あります。
この形は、ピラミッドやテントの支柱部分など、身近なところにも見られます。
三角柱と三角錐の違い
三角柱と三角錐の違いを整理してみましょう。
三角柱は、上下に同じ三角形がある柱状の立体であり、側面は長方形で構成されています。一方、三角錐は底面が三角形で、上に向かってすぼまる形をしています。
また、頂点や辺、面の数も異なり、三角柱は頂点が6個、三角錐は4個といった違いがあります。
特に大きな違いは、「柱の形をしているか、すぼまっているか」という点です。柱のような形をしているものは三角柱、頂点が1つに集まる形をしているものは三角錐と覚えておくと区別しやすいでしょう。
まとめ
今回は、三角柱と三角錐の特徴や違いについて解説しました。
これらの立体は、日常生活の中でも見かけることが多いので、実際の物を観察しながら学ぶとより理解が深まります。
次回も空間図形についてお話ししていくので、ぜひお楽しみに!