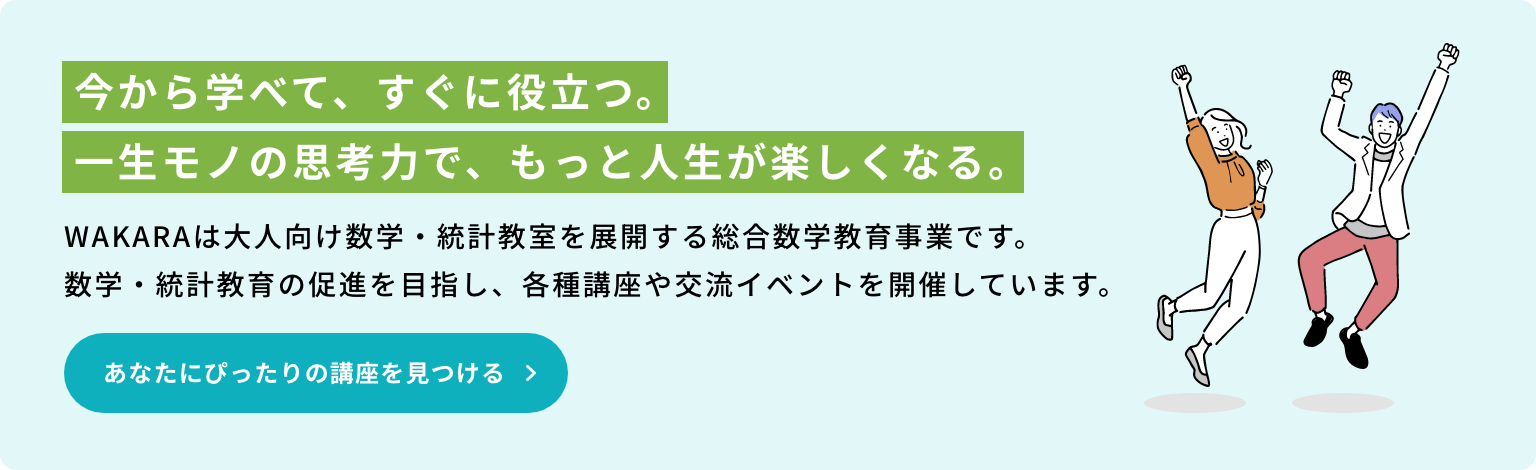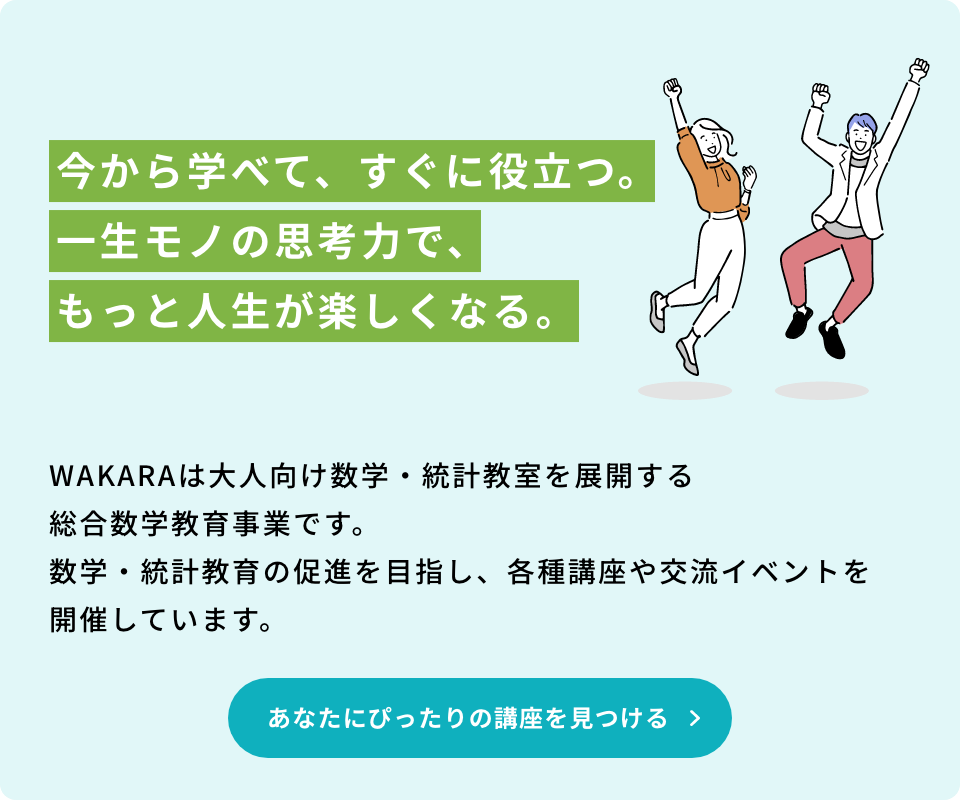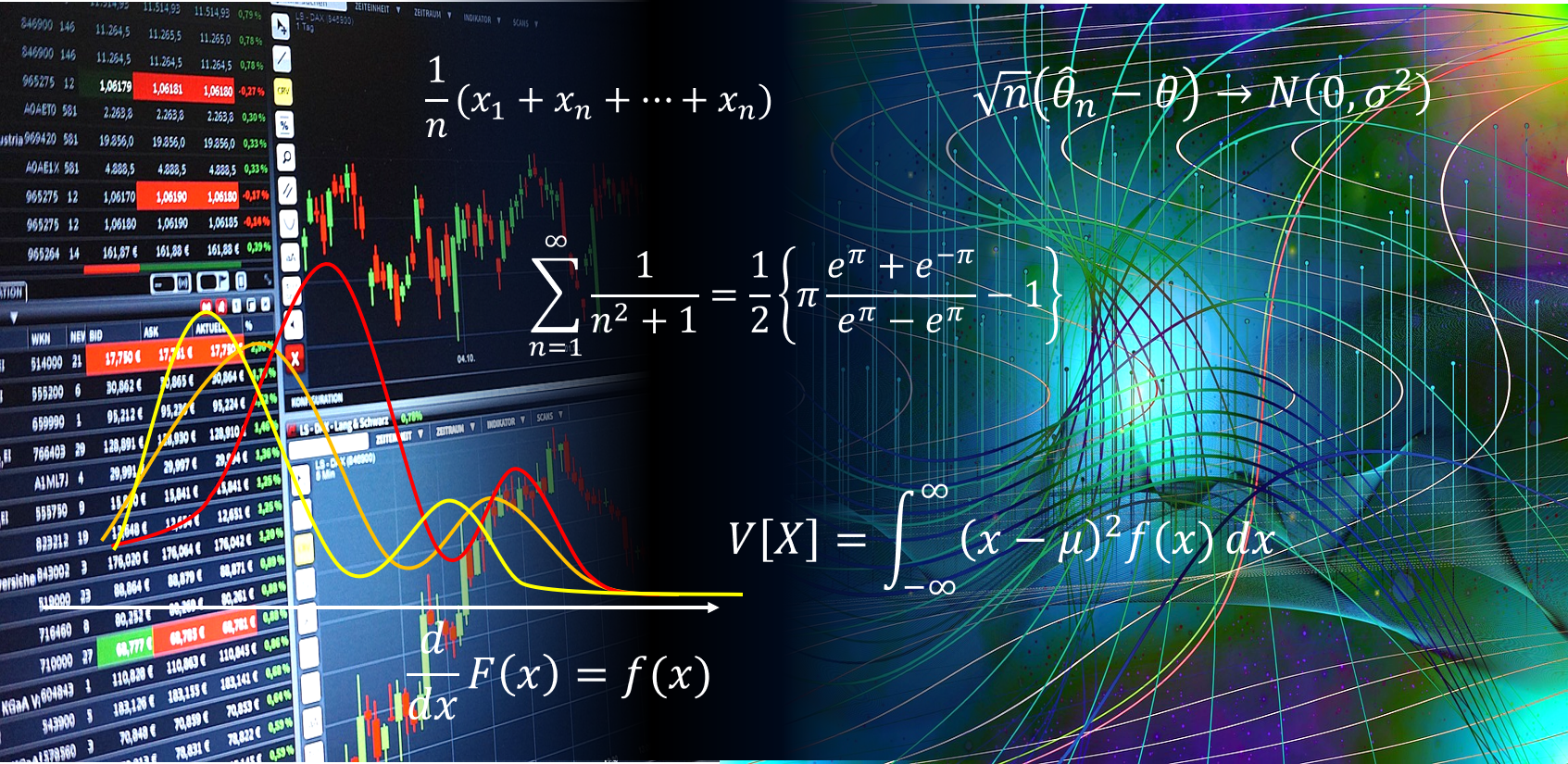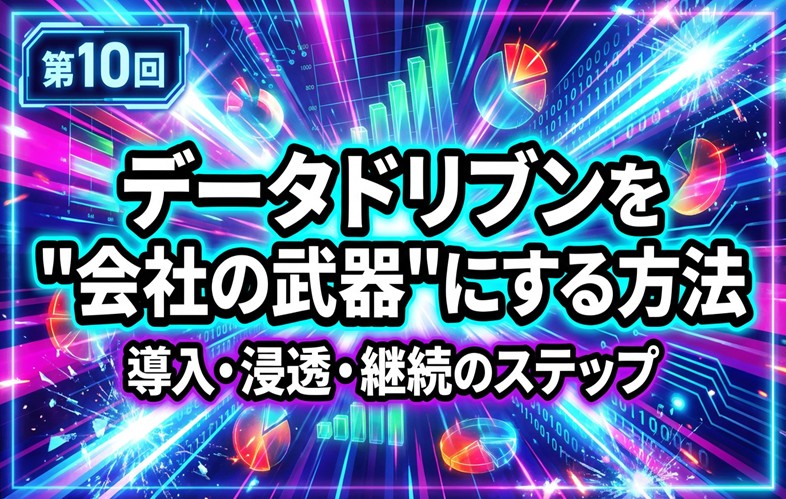大人が学ぶ算数 ―和・差・積・商って?計算の順序ときまりとは?―
公開日
2025年3月21日
更新日
2025年9月16日
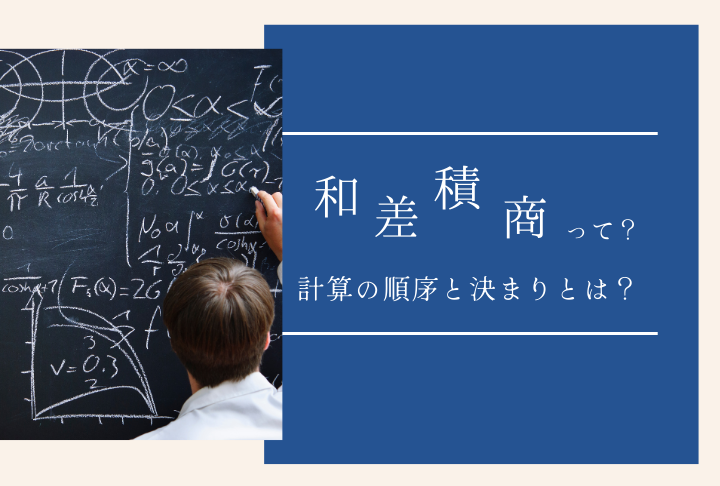
大人が学ぶ算数 ―和・差・積・商って?計算の順序ときまりとは?―
皆さんこんにちは。今回は、大人になってから改めて学ぶ「算数」の中でも、基本だけど意外と奥が深い「和・差・積・商」、そして「計算の順序」についてお話ししていきます!
大人の算数、意外と奥が深い
私が日々担当している算数の個別授業では、大人の方から「今さら聞けない」素朴な疑問をいただくことがよくあります。先日もこんなご質問をいただきました。「テキストに書いてある“和差積商”って何でしたっけ?」
きっと、学生時代には習っているはずの内容。でも大人になると日常で使うことも少なく、忘れてしまっているという方も多いのではないでしょうか?
和・差・積・商とは何か
あらためて確認してみましょう。「和(わ)」は足し算の答え、「差(さ)」は引き算の答え、「積(せき)」は掛け算の答え、そして「商(しょう)」は割り算の答えのことです。
たとえば、1+2=3 の「3」が和、3−2=1 の「1」が差、2×3=6 の「6」が積、6÷3=2 の「2」が商です。これらは四則演算と呼ばれ、私たちの生活に欠かせない基本の計算ですね。
日常生活での四則演算の例
四則演算は、日々の暮らしの中でも自然に使っています。朝昼晩の摂取カロリーを足すときは和。お買い物後の残金を考えるときは差。同じ商品を何個か買うときは積。飲み会の割り勘は商。改めて考えると、算数って思っているより身近なんです!
計算の順序ってなぜ決まってる?
では、ここでさらにこんな質問をいただきました。「なんで掛け算や割り算は足し算や引き算よりも先に計算するんですか?」
たしかに、計算は左から順番に行うのが基本。でもその中でも掛け算・割り算は優先されるというルールがありますよね。それがなぜかと聞かれると…答えるのは少し難しい。
納得のいく例を考えてみた
私なりに納得できるような例を考えてみました。たとえば、メロンパン2個とロールパン2個がセットになっている袋を3袋買ったとします。合計で何個のパンを買ったでしょう?
数式で表すと、2+2×3=8 です。もしこの順序を無視して左から計算してしまうと、2+2=4、4×3=12 と、パンの数が増えてしまうことに!実際にはパンは8個しかないのに…これは困りますよね。
ここで大切なのは、掛け算が「何かが何個分ある」という意味を持つということ。2×3 は「2が3つある」と解釈でき、つまり 2+2+2 のように足し算の繰り返しとして理解できます。
まとまりを優先する意味
掛け算や割り算が先なのは、この“まとまり”を崩さないため。バラバラに分けてしまうと本来の意味が失われてしまうんです。ルールを守って計算することは、実はこうした背景があるからなんですね。
「なぜ?」を考える算数の楽しさ
算数は、子どもの頃には「決まりごと」として暗記していたものでも、大人になってから改めて考えてみると、新しい発見があるものです。
たとえば分数の割り算で「なぜ逆数をかけるのか?」なども、よくある質問です。こうした“当たり前”に疑問を持ち、意味を理解していくことで、学び直しはグッと楽しくなります!
ということで今回は、和・差・積・商とは何か、そして計算の順序の意味についてお話ししました。次回のマスログでも、算数の「なるほど!」をお届けしていきますので、ぜひお楽しみに!