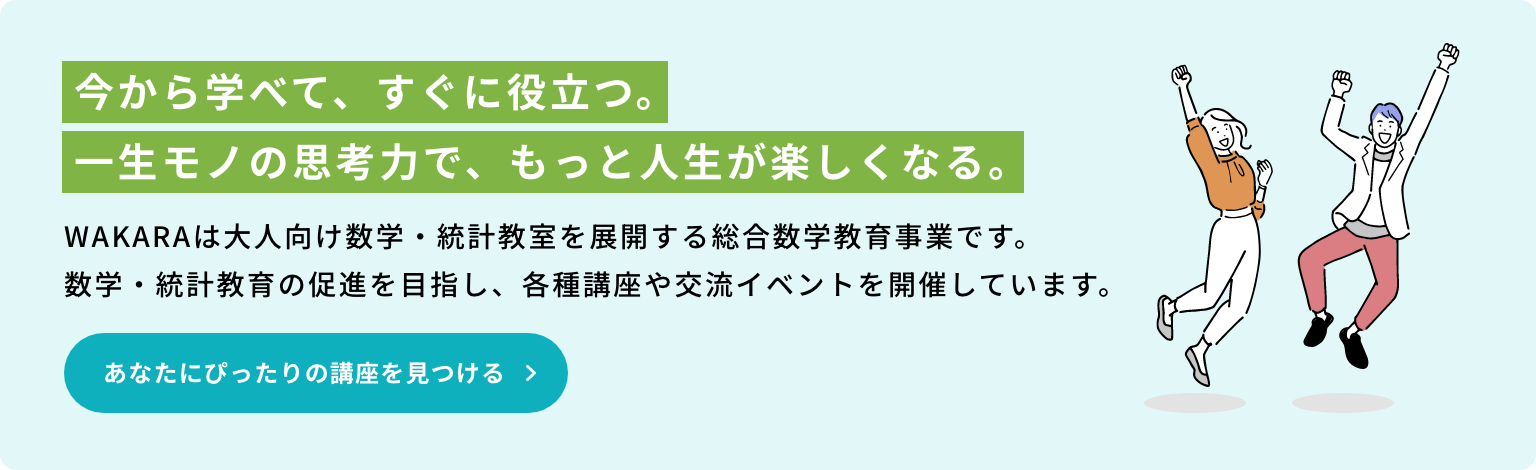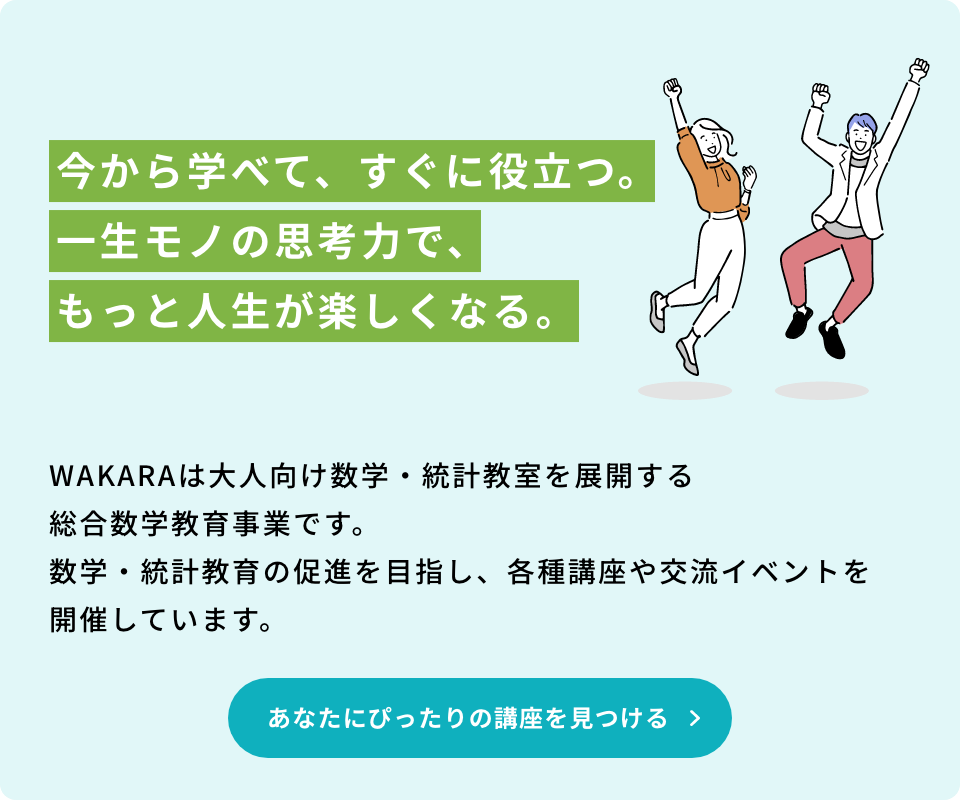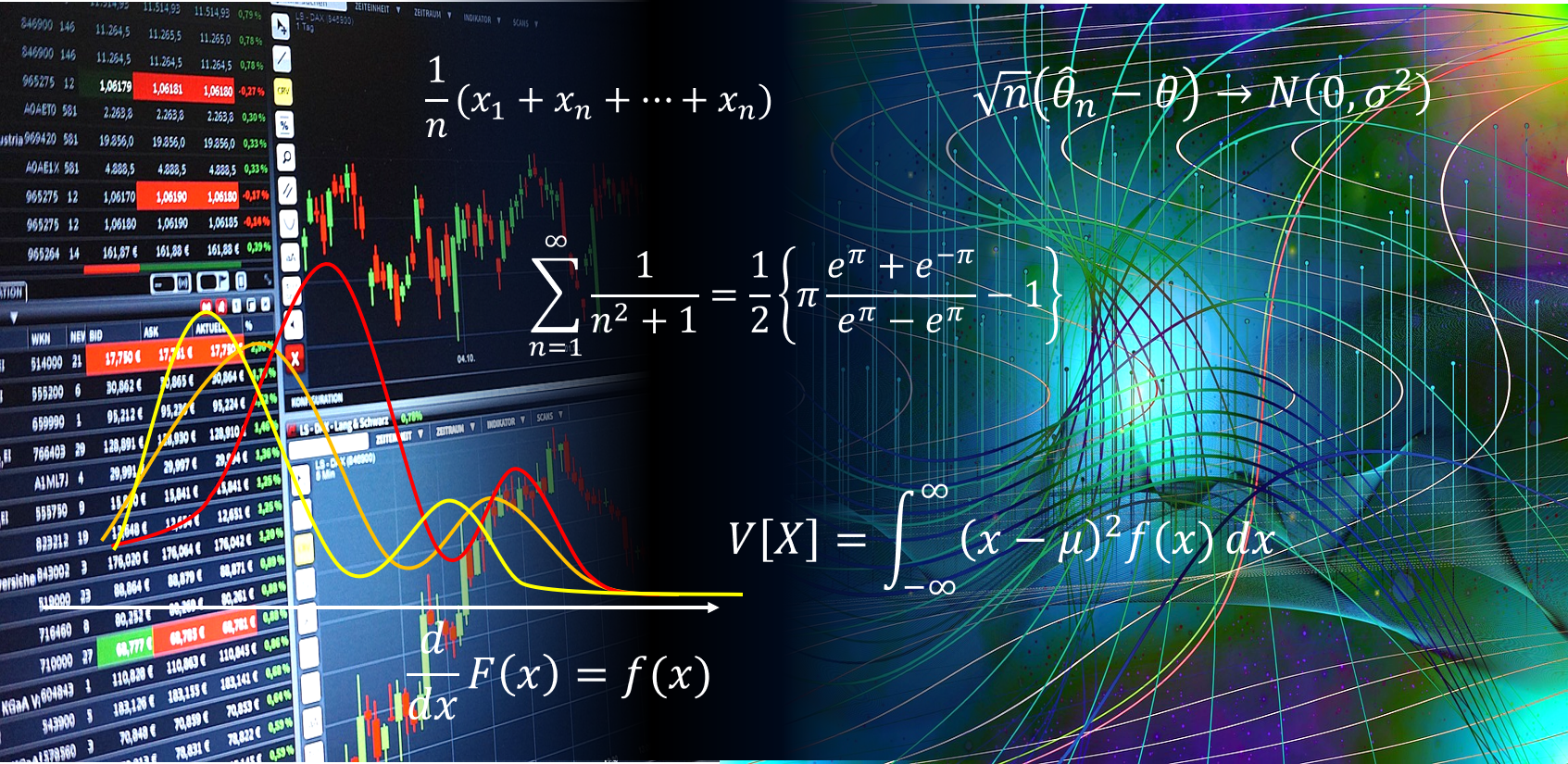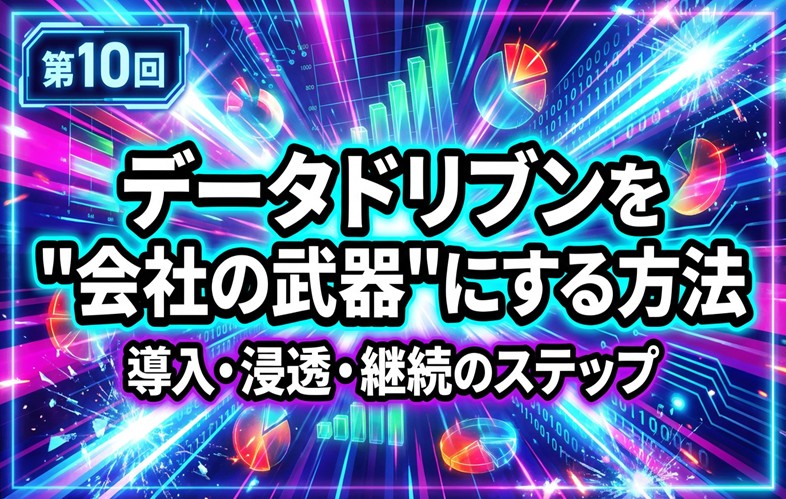【数学偉人伝】古代ギリシャの大天才!アルキメデスの功績
公開日
2025年4月9日
更新日
2025年4月9日
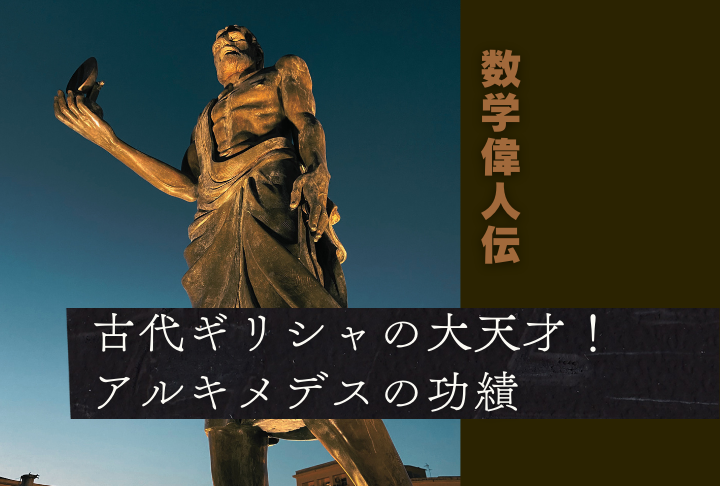
【数学偉人伝】古代ギリシャの大天才!アルキメデスの功績
こんにちは。今回は「数学偉人伝」として、古代ギリシャの天才、アルキメデスの生涯と功績についてご紹介したいと思います。科学の世界を学ぶうえで必ず登場する名前ですが、彼の数ある業績の中でも、特に私が感動したものをピックアップしてお話ししていきます。
アルキメデスとはどんな人物?
まずは、アルキメデスという人物がどんな人だったのかを見ていきましょう。彼は古代ギリシャ時代の数学者であり、科学者としても知られています。シチリア島のシラクサという都市国家で研究に没頭し、多くの発見を行いました。
王に信頼されるほどの頭脳の持ち主で、数学や物理にとどまらず、国防のための兵器を設計するなど、実用面でも大きな力を発揮していたと言われています。特に投石機のような装置を用いて、当時強大だったローマ帝国から街を守るために貢献したという記録も残されています。
また、現代においてもアルキメデスの偉大さは語り継がれており、数学界で最高の栄誉とも言われるフィールズ賞のメダルにも、彼の肖像が刻まれています。これだけでも、どれほどの影響を与えた人物かが伝わると思います。
浮力の発見とアルキメデスの原理
次に紹介したいのが、アルキメデスによる「浮力」の発見です。浮力というのは、水中で物体が受ける上向きの力のことですが、同じ形でも重いものは沈み、軽いものは浮くという不思議な性質があります。
この浮力を理論的に説明し、「アルキメデスの原理」として知られる法則を発見したのが彼なのです。面白いのは、この発見にまつわる逸話です。
ある日、当時の王様から「純金で作られたはずの王冠に銀が混ざっているという噂がある。確かめてほしい」と依頼されます。とはいえ、王冠を壊したり削ったりするわけにもいかず、アルキメデスも頭を悩ませていました。
ところが、ある日お風呂に入ったとき、浴槽からこぼれ出るお湯を見て「これだ!」とひらめいたのです。そして実際に王冠と同じ重さの純金の塊を用意して、それぞれを水に沈めたところ、水から溢れ出す量が異なることに気づきました。
これにより、王冠には純金以外の金属が混ざっていることが明らかになったのです。まさに発想の勝利ですね!
円周率の近似と取り尽くし法
アルキメデスのもう一つの大きな功績として、私は「円周率の近似」に関する話が特に印象的です。円周率といえば、3.14159…と無限に続く数字で知られていますが、古代の時代にそれを正確に求めようとしたこと自体が驚きです。
円周率とは「円の直径に対する円周の長さの比」のことで、円の性質を表す重要な数です。当時、正確な値を求めるためにはどうすればいいかを考え、アルキメデスは円の中に内接する正多角形を使うという方法を思いつきました。
多角形の辺の数を増やせば増やすほど、円に近づいていきます。この「取り尽くし法」と呼ばれる手法により、彼は円周率が3.1408から3.1429の間であると計算しました。現代の正確な値と比べても、かなりの精度で近似できていたことが分かります。
この方法は、のちに積分の考え方にもつながっていく発想であり、当時としてはまさに画期的な試みだったのです。
アルキメデスの意外な最期
これだけの偉業を成し遂げたアルキメデスですが、その最期はあまりにも突然で衝撃的なものでした。
当時、彼が暮らしていたシラクサはローマ帝国との戦争状態にありました。そしてある日、ローマ兵が街に侵攻してきた際、アルキメデスは地面に図形を描いて問題を考えていたとされています。
実はローマ側にも彼の名は知られており、命を奪ってはならぬという命令が出ていたそうです。しかし、彼の姿を知らなかった一人の兵士が図形の上に足を踏み入れ、それに怒ったアルキメデスが「私の図を踏むな!」と叱りつけたことで、その兵士の怒りを買って命を落としてしまったというのです。
これが事実かどうかには諸説ありますが、もし彼がその後も生きていれば、さらに多くの発見をしていたかもしれないと思うと、惜しまれてなりません。
ここまで、古代ギリシャの大天才・アルキメデスについてご紹介してきました。彼の功績は、数学や科学の歴史の中で今なお輝き続けています。
次回もぜひご覧ください!