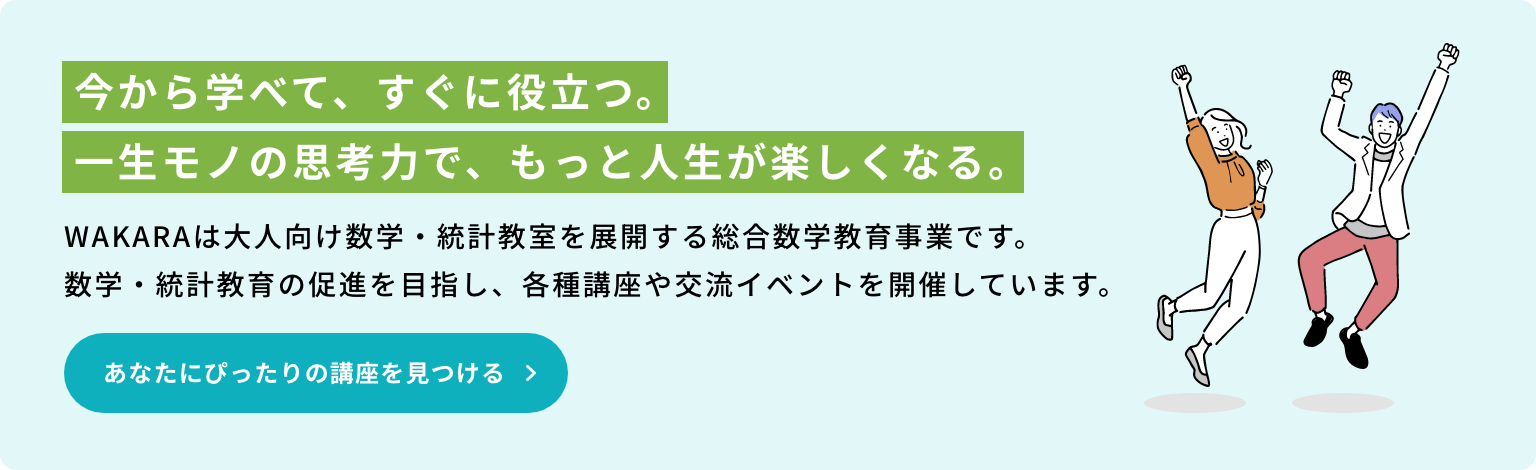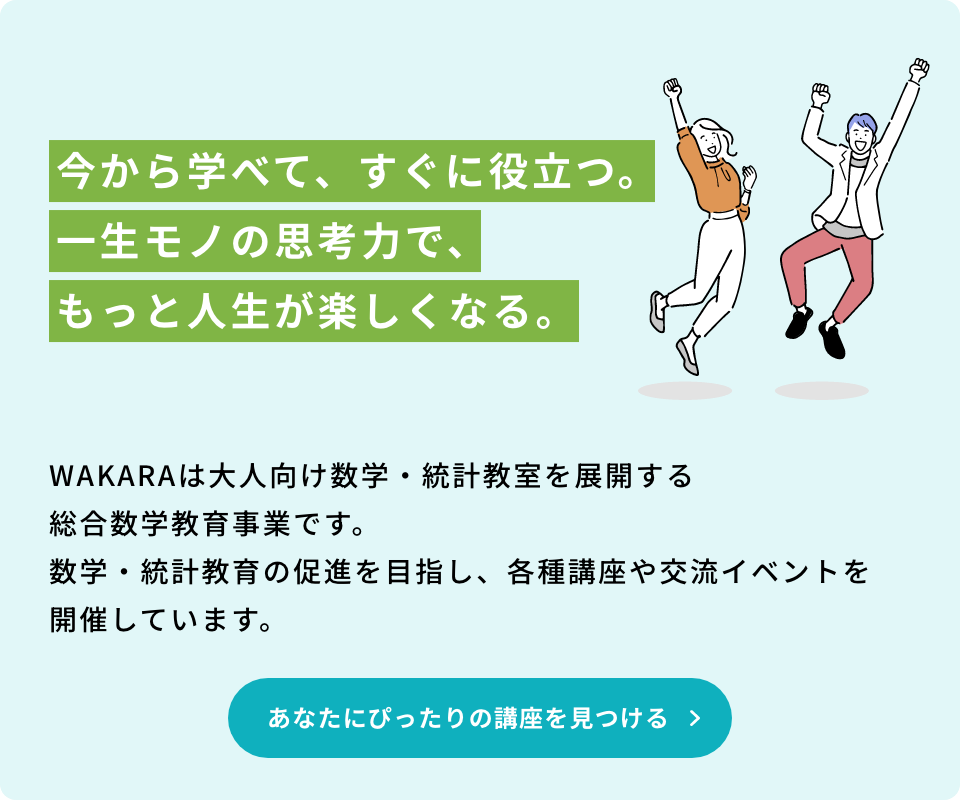考える力 因果推論って何?
公開日
2024年12月16日
更新日
2025年1月19日
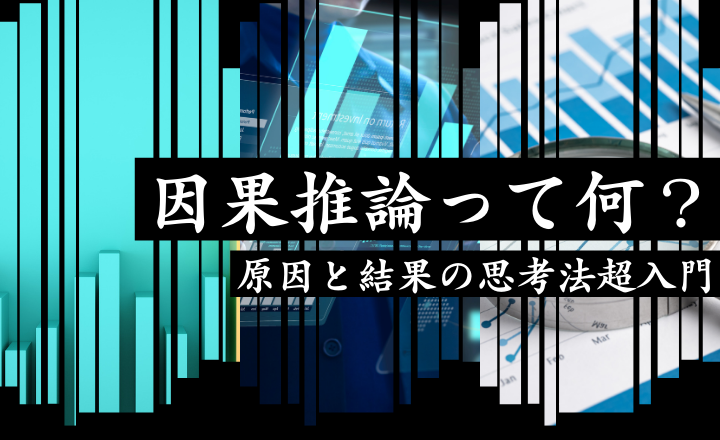
和から株式会社:無料講座
【原因と結果の思考法超入門】で行う内容のダイジェストです。
考える力を鍛えたい!論理的思考ができるようになりたい!
因果関係ってどういうこと?
はじめて論理的思考や因果関係、考える力を学びたい方にこそ見てほしいです。
因果推論って言葉は難しいですが、内容はシンプルです。
▷【無料セミナー申込ページ】
➡ https://wakara.co.jp/course/7829
▷【WAKARA WEB:数学は大冒険だ】
▷【大人のための教室 Facebook】
▷【大人のための教室 instagram】
▷【大人のための教室 Twitter】
因果推論のノーベル賞
去年、ノーベル経済学賞を受賞したバナジ教授、ディ・フェロー教授、クレーマー教授の研究が話題になりました。彼らが注目された理由は、経済分析に因果推論を導入したからです。もともと医療や疫学で使われていた因果推論を、経済学の分野に適用したことが評価され、ノーベル賞を受賞しました。彼らの研究は、特に貧困層の改善に向けた施策の効果をデータに基づいて明確に示した点が評価されています。
貧困層のための実験
彼らは、発展途上国の子供たちが学校に通えるようにするため、どの施策が一番効果的かを調べるために、さまざまな実験を行いました。例えば、教員の増加や給食の提供、制服の整備など、いくつかの施策を打ちました。では、皆さんはその中で一番効果的だと思う施策は何だと思いますか? ちなみに、私も最初は「給食」が一番効果的だと思っていました。
意外な結果
実際にデータを分析してみると、一番効果があった施策は「虫下し薬の給付」と「教育リターンに関する情報提供」でした。意外ですよね? 虫下し薬は、発展途上国では子供たちが寄生虫に感染していることが多く、その結果として学校に通えないことがあるのです。薬を提供することで、体調が改善し、学校に通うことができるようになったという結果でした。また、教育に対するリターン(将来の収入に関する情報)を親に提供することで、子供たちが教育を受ける意義を理解し、学校に通うようになったということです。
認識と事実の違い
この研究を通じて、私たちが思っている「常識」と実際の事実が異なることに気づかされました。私は最初、給食が一番効果があると思っていましたが、データを基にした実際の結果は全く違っていました。このように、私たちの直感とデータに基づく事実は必ずしも一致しないことがあるのです。だからこそ、因果推論を使ってデータから真実を導き出すことが重要だということがわかります。
次回も、もっと面白いデータの裏側を探っていきますのでお楽しみに!