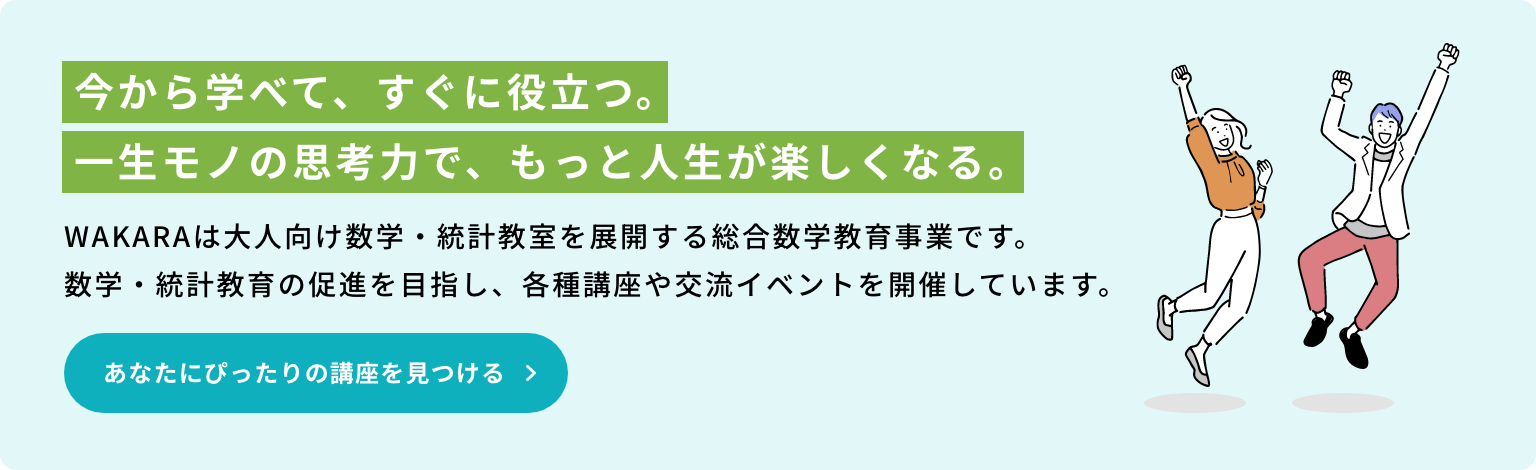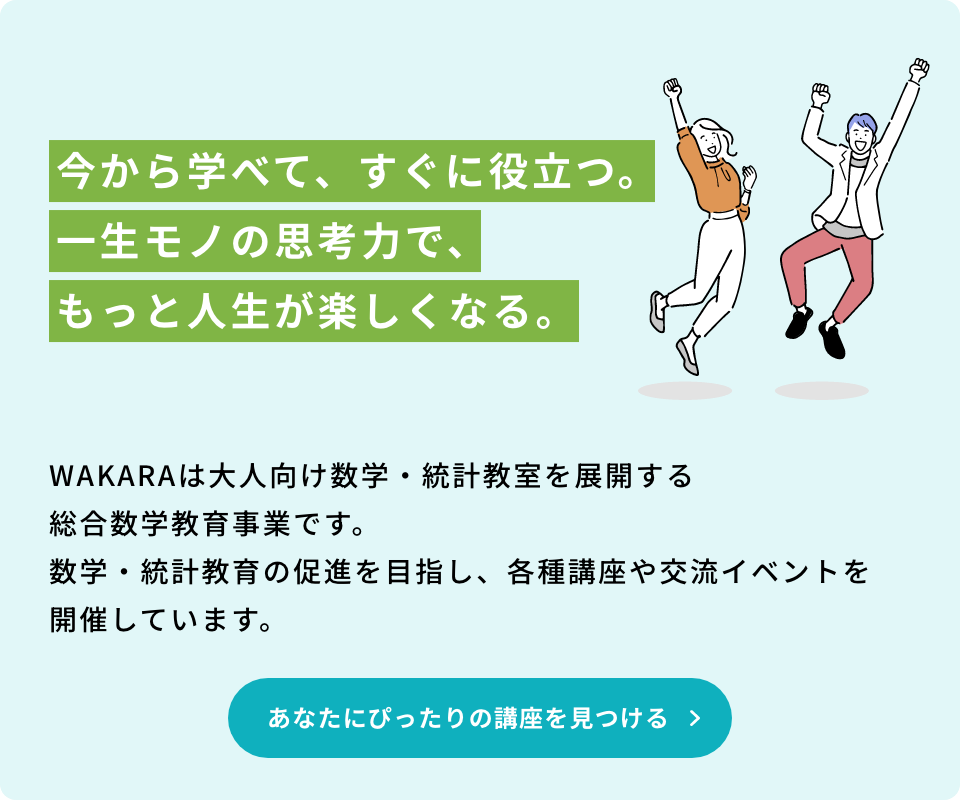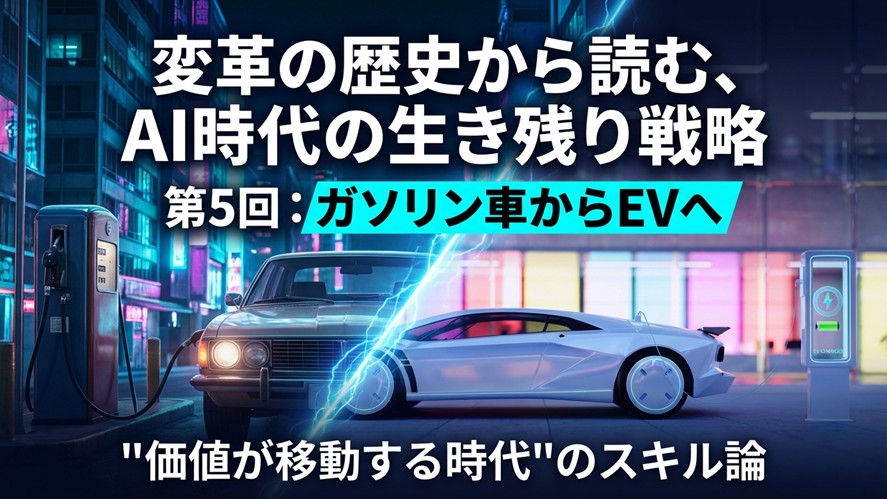【算数からやさしく解説】筆算とは?
公開日
2025年3月18日
更新日
2025年9月16日
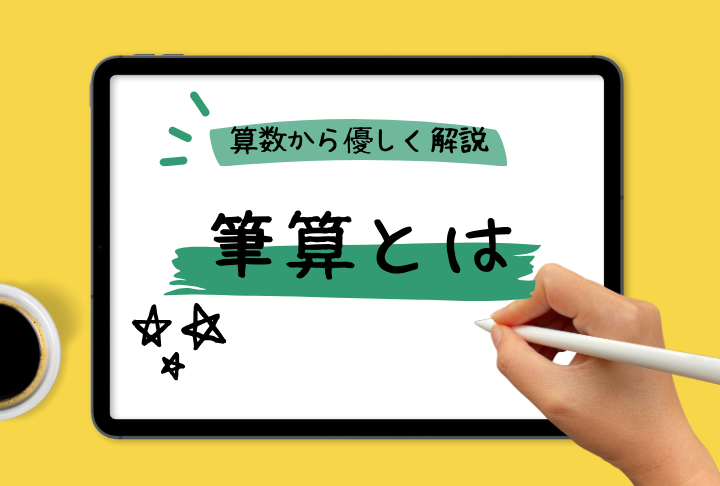
【算数からやさしく解説】筆算とは?
皆さんこんにちは。今回は「筆算とは何か?」というテーマで、算数の基礎の基礎を改めて見つめ直していきたいと思います。第0回目という位置づけで、筆算の仕組みや活用例までやさしくご紹介していきます!
筆算とは何か
筆算とは、紙に書きながら行う計算方法のことです。小学校で誰もが習う代表的な計算スタイルで、加減乗除すべてに対応しています。
筆算以外の方法としては、暗算やそろばん(珠算)などもありますが、筆算は計算の過程を紙に書いて「見える化」するため、誰が見ても理解しやすく、どこで間違えたのかも分かりやすいという大きな利点があります。
足し算の例
筆算の基本として、35 + 29 の計算を考えてみましょう。まず1の位、5 + 9 = 14 となり、4を下に書いて、繰り上がりの1を上に載せます。そして10の位、3 + 2 = 5 に繰り上がりの1を加えて6。結果は64となります。
この過程は、35と29を「30 + 20」と「5 + 9」に分けて処理しているとも言えます。数字の分解・再構築の視点を持つことで、計算の背景が見えてくるのが筆算の面白さですね。
かけ算の例
では掛け算、例えば 35 × 29 も見てみましょう。これは 35 × (20 + 9) と分解できます。さらに分配法則を使って、30 × 20、5 × 20、30 × 9、5 × 9 と計算を進めていくと、それぞれの積を合計して 1015 になります。
複雑な掛け算でも、このように一つひとつのステップを可視化していけば、間違えずに計算することができるのです。
筆算のデメリット
筆算の弱点を挙げるとすれば、それは「紙と手間が必要なこと」です。現代では電卓やExcelなどのツールが発達しており、実生活ではそちらを使う方が速くて正確です。そのため、筆算を実際に使う場面は減ってきています。
筆算の活用と意義
とはいえ、筆算の持つ価値は今でも大きいです。筆算によって計算の仕組みを可視化することは、暗算力の向上や、計算アルゴリズムの理解に繋がります。実際、コンピューターで行われる計算も、基本の発想は筆算の仕組みと共通している部分があります。
つまり、筆算は「計算そのものの理解を深める手段」として、今でも非常に有効なのです。
おわりに
弊社ではこういった数字に強くなるための無料セミナーも開催しております。筆算に限らず、数字の扱いをもっと上達させたいという方は、ぜひご参加いただければと思います。
ということで、今回は「筆算とは?」というテーマでお届けしました。それでは、また次回のマスログでお会いしましょう!