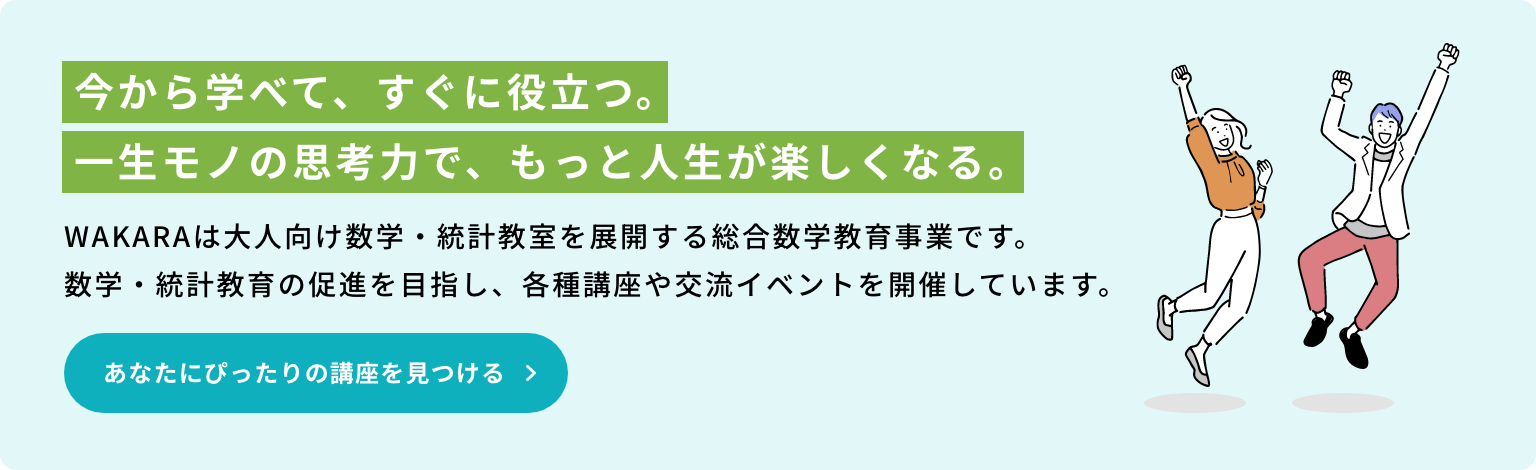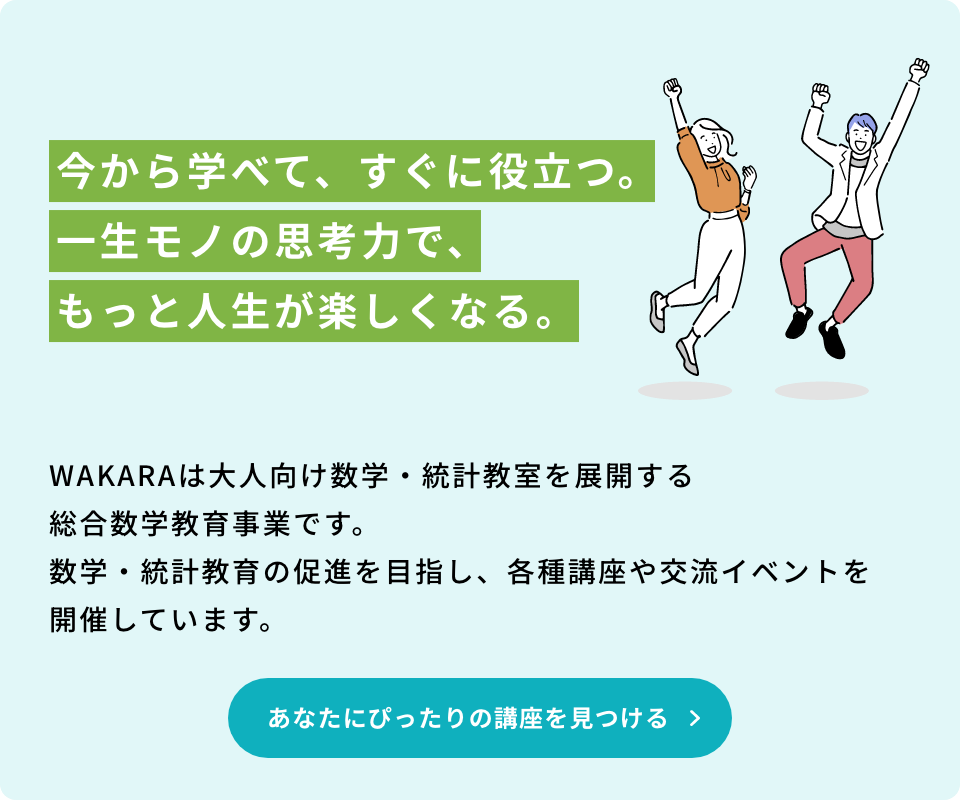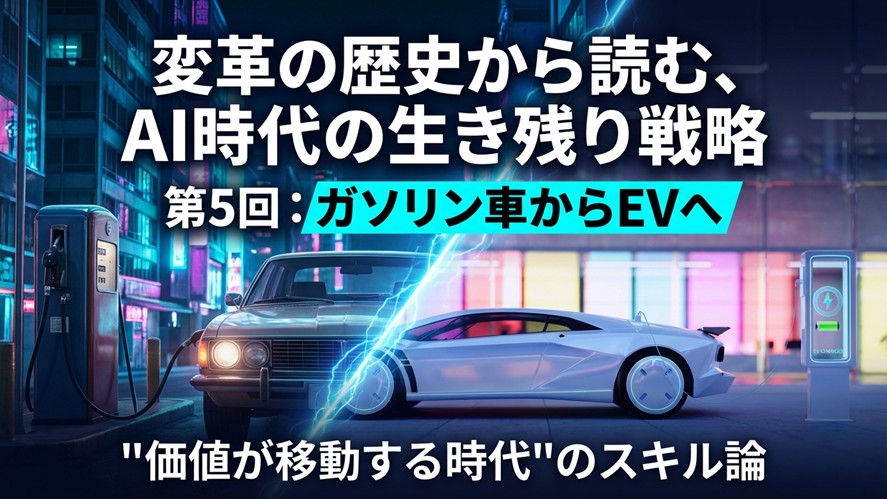【数学偉人伝】20世紀最高の物理学者!アインシュタインは何をした人物?
公開日
2025年3月9日
更新日
2025年4月13日
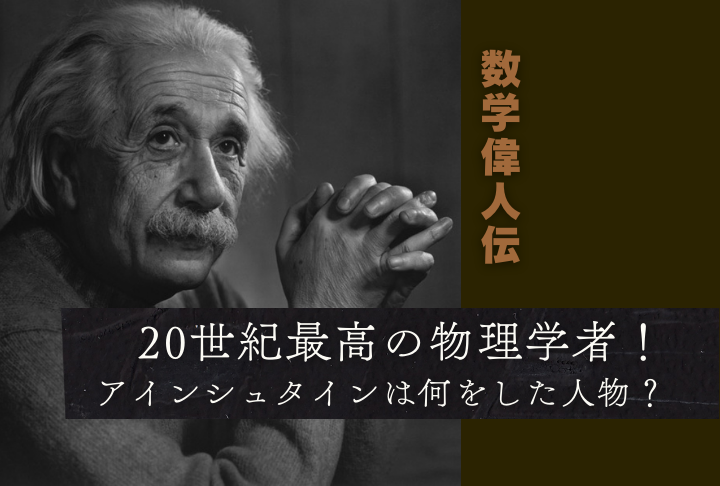
【数学偉人伝】20世紀最高の物理学者!アインシュタインは何をした人物?
皆さんこんにちは。今回は「数学偉人伝」として、20世紀最大の理論物理学者アルベルト・アインシュタインについてご紹介します。
この記事が書かれているのは3月14日。ホワイトデーであると同時に、円周率「3.14」にちなんだ日でもありますが、実はアインシュタインの誕生日でもあるのです!この日を選んで生まれてきたのは偶然ではないのでは…とすら思ってしまいます。
彼は現代の技術、たとえばロケットや人工衛星、半導体やコンピューターの基礎を築いた理論を打ち立てた人物でもあります。今回は、そんなアインシュタインの人生と、その偉大な功績を3つご紹介していきたいと思います。
アインシュタインとはどんな人物?
アルベルト・アインシュタインは、1879年にドイツ南西部のウルムという街で生まれました。幼い頃は言葉での表現が苦手で、5歳頃までほとんど話さなかったとも言われています。
けれど、数学や物理への興味は並外れていて、9歳のときにはピタゴラスの定理を独力で証明し、14歳では叔父からもらったユークリッド幾何学の本を夢中になって読み、その正確さに強く惹かれたそうです。
一度の浪人を経てチューリッヒ連邦工科大学(現在のETHチューリッヒ)に入学し、1900年に卒業。その後は家庭教師や臨時の仕事で生活を支えながら、スイスのベルンに移り住み、1902年に特許局で働くようになります。この職場での安定が、彼の研究活動に大きく貢献することになります。
光の量子論の提唱
1905年、アインシュタインは立て続けに3本の画期的な論文を発表します。その最初が「光の量子論の提唱」です。これは、光が波であると同時に粒としてもふるまうという性質を示したもので、当時としては極めて革新的な考え方でした。
当初はほとんど注目されませんでしたが、後に多くの科学者たちがその考えをもとに量子力学を発展させ、現代の半導体技術やコンピューター、家電製品の基礎が築かれました。1921年、アインシュタインがノーベル物理学賞を受賞したのも、この功績によるものです。
ブラウン運動と原子の実在証明
2本目の論文では、「ブラウン運動」と呼ばれる現象について取り上げています。これは水面に浮かぶ花粉のような微小な物質が、不規則に動き回るというものです。
アインシュタインはこの運動が、水分子との衝突によるものだと考え、その動きを計算で予測しました。この理論は1908年にジャン・ペランという科学者によって実験的に証明され、原子が実在することを世界に示した大きな一歩となりました。
特殊相対性理論の構築
そして3本目が、アインシュタインの代名詞とも言える「特殊相対性理論」です。彼はこの理論によって、光の速度が一定であること、そして時間と空間が絶対ではなく「相対的」に変化するという事実を示しました。
特に「時間は誰にとっても同じ速度で流れるものではない」という発想は、当時の常識を根底から覆すものだったのです。彼がこの概念を説明するために例え話として語った有名な言葉があります。
「可愛い女の子と1時間一緒にいれば、1分しか経っていないように思える。でも、熱いストーブの上に1分座らされたら、1時間よりも長く感じる。相対性とは、これである。」
もちろん、正式な論文ではきちんとした計算で示されていますが、こうした例えにもアインシュタインの人柄がにじんでいます。
科学を進化させたロマンチスト
この特殊相対性理論はのちに「一般相対性理論」へと発展し、現代物理学の土台となります。月面着陸やGPS、原子力エネルギーなど、私たちの暮らしに密接に関わる技術の多くは、アインシュタインの理論なしには成立しなかったのです。
奇跡の年とも呼ばれる1905年、わずか数か月の間に発表されたこれらの論文によって、彼は科学の歴史に名を刻みました。アインシュタインは生涯を通じて、世界への純粋な好奇心を持ち続け、物の見方を何度も塗り替えるような発見を残していったのです。
そして最後に、3月14日らしいアインシュタインの名言をひとつご紹介して終わりにしたいと思います。「恋に落ちるのは、重力のせいにはできない。」
重力の正体を解き明かした彼でも、恋の理屈だけは解明できなかったのかもしれません。そこにまた、科学者としての彼のロマンを感じてしまいますね。
ということで、今回はアインシュタインという偉人の足跡をたどってみました。次回の【数学偉人伝】も、ぜひお楽しみに!